38・5・1 OCTの進展
光コヒーレンストモグラフィー(OCT:optical coherence tomography)の原理は,低コヒーレンス光干渉を利用した高分解能な反射点の検出に基づく.1987年,高田らによって低コヒーレンス光干渉計を用いた光導波路の故障診断が報告された43).この測定法はOCDR(optical coherence domain reflectometry)と呼ばれ,空間分解能10 μmの高精度調長法として限径測定などに利用された44).そして,1990年,丹野らがOCTの原型ともいうべき光波反射像測定装置を発案・特許出願した45).その翌年,J.G.Fujimotoのグループ(MIT)からOCTの論文発表があり46),その後,米国では驚くべき速さでOCT技術が進展し,1996年に早くも眼科用OCT装置が市販された47).これに続いて,2002年春には皮膚観察用OCTが市販された48).さらに,消化器外科,産婦人科,泌尿器科等々でOCTの臨床応用が検討されている49)50).
このように,OCTは提案からわずか5年余で実用化された画期的な光技術である.このOCTの急速な進展は,生体中における散乱の影響を巧みに除去して,μmオーダーの高分解能な断層イメージングができることにある.また,使用する光波長城が光通信帯と一致しており,光エレクトロニクス技術を駆使できるのも大きな利点である.しかし,この反面,生体表皮下における光の到達深度の向上,断層イメージの空間分解能の改善,幾何学的サイズでのイメージンク等々,解決すべき基本的な技術課題も多い.
本節では,OCTの原理と基本的な特性,医療診断応用,技術課題の解決策を含むOCT の技術展開および今後の展望について述べる.
38・5・2 OCTの原理
OCTではマイケルソン干渉計を用いて断層イメージを取得する.干渉計には時間コヒーレンスの低い光源を用いる.光源の発振波長スペクトルがガウス分布であるとき,その中心波長をλc、半値全幅をΔλとして,光源のコヒーレンス長Δlc(マイケルソン干渉討における可干渉距離)は、

となる51).市販の0.8 μm帯SLDでは,λc=850 nm,Δλ=16 nmであり,Δlc=20 μmである.Δlcは光波の電界の時間軸上における変化からも推定できる.低コヒーレンス光では正弦波振動はごく短時間に間欠的に発生する.この正弦波振動の持続時間をΔt,光速をcとして,2Δlc=cΔtである.
SLDを光源とする低コヒーレンス干渉計を図38・15(a)に示す52)53).SLD出射光は半透明鏡(BS)で二分され,一方はミラーで反射されて参照光となり,他方は生体に照射され,その反射光は光検出器の手前で参照光と干渉する.生体からの反射光の中には,散乱によって波面がひずんだ光波が多く含まれる.しかしながら,参照光は平面波であるので,反射光の中で平面波を保持した成分のみが参照光と干渉する.すなわち,干渉を利用して散乱の影響を受けない直進光成分のみを選択的に検出できる.
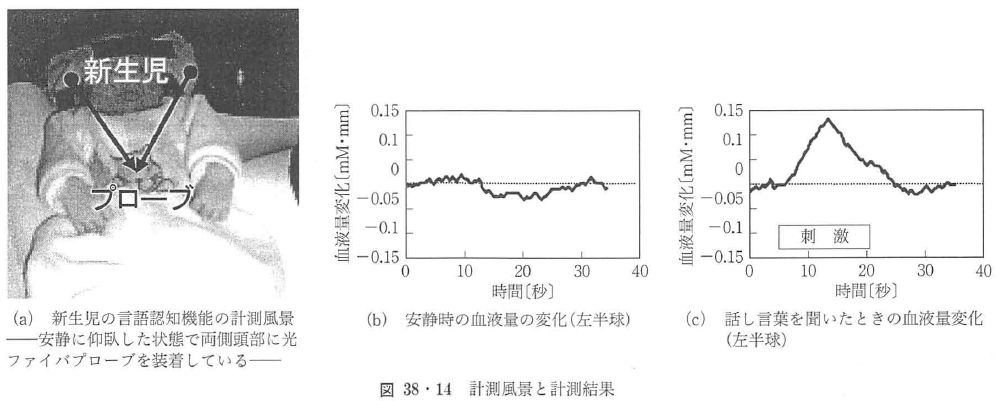
ここで,生体中の異なる反射点A,B,Cを考える.生体中の反射点AとBSとの距離Lsと参照光ミラーの位置AとBSとの距離LRとの差がコヒーレンス長の範囲内であれば(|LR-Ls|<Δlc),時間軸上で反射光Aと参照光Aが重なり,両者は干渉して検出信号を得る(図(b)).このとき,反射光B,Cは参照光A と干渉しない.そこで,参照光ミラーを位置AからB,Cへと移動すれば,順次反射光B,Cを選択的に検出できる.すなわち,参照光ミラーの位置と生体中における反射点の位置はΔlcの範囲内で1対1に対応している.したがって,参照光ミラーを連続的に移動して干渉信号を検出すれば(OCTのAモード走査),生体中における光軸方向の反射光強度分布が得られ,これがOCTのラスタ信号となる.そこでx方向に沿って生体への入射光位置をステップ状に移動し,各ステップごとにミラーを光軸方向(z方向)に走査すれば,紙面内(x-z面内)での断層イメージが得られる(Bモード走査).
このOCTの特長は,いかなる画像再構成技術を必要とせず,干渉信号を検出して,信号強度をそのままパソコンの画商上に擬似カラー表示するだけで簡単に断層イメージが得られることにある.
38・5・3 ファイバ干渉計とOCTの基本特性
無料ユーザー登録
登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。
- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。
- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。
