幅広い応用が期待されるテラヘルツ波 ─ 解像度や感度の向上が着々と進む
テラヘルツ波の有用性は古くから認識されており、物性、生体観察、通信、セキュリティなどあらゆる方面から発生・検出への挑戦が続いてきた。近年さらにその取り組みは活発になっており、画像の解像度や検出感度の向上が報告されている。
テラヘルツ波は周波数でいうと0.1~10THz、波長に換算すると3mm~30μm程度で、電波と可視光・赤外光の間にあたる領域の電磁波である。プラスチックや紙等に対する透過率が高いことや生体に害を与えない、材料物性を調べるのに有用であるなどさまざまな特性をもつ。しかし光源・検出ともに適切なものがなかったため、電磁波利用における谷間とも呼ばれてきた。
光源における可視光・赤外光側からのアプローチではレーザの利用が試みられてきた。ところが、通常の半導体レーザでは、レーザ光発生に利用する電子のエネルギー準位間隔は可視光や近赤外光周辺のエネルギーに等しく、電磁波のエネルギーはテラヘルツ帯に向けて低くなるため、一般にレーザ発振は困難になる。いっぽう電波の側からは電子の高速制御によるテラヘルツ波の発振が試みられているが高周波になるにつれて発振パワーは下がってしまう。日本では1950年代からテラヘルツ波の重要性が指摘されており、江崎玲於奈氏によるブロッホ発振器の提案、西澤潤一氏によるラマンレーザ、霜田光一氏によるガスレーザなどの取り組みがあった。
近年、電波側からの発振器としては、共鳴トンネルダイオード等の利用がある。2010年には東京工業大学の鈴木左文氏、浅田雅洋氏らが、共鳴トンネルダイオードを使い、初めて室温で1.04THzのテラヘルツ波を発生させることに成功している。この時の出力は7μWだった。一方、光側からのアプローチとしては、2つの赤外レーザによる差周波発生、量子カスケードレーザなどが注目されている。量子カスケードレーザについては動作温度は100~200Kと低いものの研究開発向けに販売されており、化学分析や工業検査などに使われているという。またこういった要素技術の開発研究とともに、理化学研究所と情報通信機構(NICT)により、テラヘルツ領域におけるさまざまな材料の吸収スペクトルの膨大なデータベースを作製するなどの取組みも進んでいる。
発生と並ぶもう1つの主要技術である検出器については、室温での動作実現を目指すものと、低温のまま感度やスピードなどの性能を追求する方向に分かれると東京工業大学 量子ナノエレクトロニクス研究センターの河野行雄准教授はいう。従来からの検出器は、冷却が必要なボロメータや室温動作の焦電検出器、室温動作のショットキーバリアダイオードなどがある。
有望だと見られているものの一つが超伝導検出器だ。主に2つのタイプがあり、1つは、入射したテラヘルツ波によって発生する超伝導体におけるトンネル効果を利用するジョセフソン接合素子である。もう1つは、微小な超伝導素子を用いたボロメータであり、とくに超伝導を発現する付近の温度を維持しておくと、わずかな電磁波の吸収によって抵抗が大きく変化するため感度が高くなる。また別の検出機構として半導体におけるプラズモンを使う手法も研究されている。通常の電子を励起するよりもプラズモンの電気振動を読み出すため高感度になる。
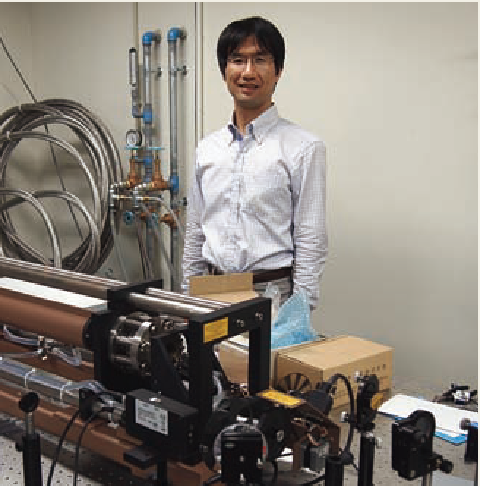
東京工業大学の河野行雄准教授とテラヘルツ実験装置
近接場光利用とパッシブ顕微計測
河野氏の研究室では、テラヘルツ波の検出器や画像化技術について、常温動作に限らず極限性能の追求をテーマに研究を行っている。具体的には、画像計測の解像度、検出感度の追求、そして分光システムの3 つの主要な要素技術の開発に取り組んでいる。
(もっと読む場合は出典元へ)
出典元
https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2012/12/201210-11_0018Introlabo.pdf
