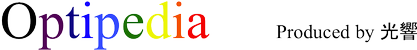埋込型蛍光ビーズで血糖値変化をリアルタイム検出
東京大学生産技術研究所と技術研究組合BEANS研究所は、血糖値に応じて光の強度を変化させるハイドロゲルを微細加工し、直径100μm 程度の均一径のビーズ作製に成功した。さらに、これらのビーズをマウスの耳に埋め込み、周辺のブドウ糖の濃度に応じて変化する蛍光輝度を体外から計測することにも成功した。
現在、世界の糖尿病患者は2.4億人、世界保健機関(WHO) によると2025 年にはこの数は3.8億人に達すると予測されている。糖尿病では、失明、腎臓障害などの合併症を防ぐために血糖値管理は必要不可欠。血糖値は、食事や運動によって大きく変動するため、1日数回の計測では、十分な経時変化をとらえることは難しい。24時間連続して、長期にわたり血糖値計測が行なえる方法が切望されている。
現在、一般的な血糖値センサは採取した血液から血糖値計算する簡易血糖値検査で、4~5時間に1回程度の間欠検査となる。半埋込型のセンサを利用すると5 分おきに計測できるが、これは皮下に針を埋め込むため、感染症を引き起こす可能性があり、3~7日おきに針の抜き差しが必要になる。しかし、継続検査ができて数ヶ月の連続使用に耐えうる血糖値センサは開発されていないという。
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 「異分野融合型次憔代デバイス製造技術開発プロジェクト」(BEANSプロジェクト)では、プロジェクトの一環として埋込型血糖値センサの開発が進められている。
100μmマイクロビーズ作製
完全体内埋込型の血糖値センサの開発がBEANS研究所准教授の竹内昌治氏の研究グループの目標。研究グループは、まずは生体適合材料を微小化することから始めた。ここで用いている材料はポリアクリルアミドゲル。ポリアクリルアミドゲルは、すでに様々な埋め込み材料に使われている。そのゲルに蛍光色素を共有結合させて蛍光ポリアクリルアミドゲルとする。ゲルは、ブドウ糖(グルコース)を吸収すると蛍光強度が上昇するが、今回はゲルをマイクロビーズにする技術を開発した。
マイククロビーズにする理由について竹内氏は「100μmサイズのビーズにすることによって、埋め込みがしやすくなる」と説明している。
生産技術研究所にマイクロ流体デバイス技術があり、それを使うとこのような溶液を小さなビーズにすることができる。同軸状の円環中央にゲルの元になる溶液を人れ、外側には袖を入れる。AFDというデバイスによって溶液が液滴になる、それを37℃まで温めるとゲル化する。研究グループが調べた粒径分布では、作製されたビーズは直径130μm程度に集中している。
(もっと読む場合は出典元へ)
出典元
https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2009/08/200908_wn05_1.pdf